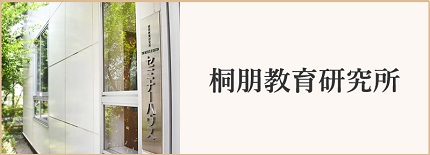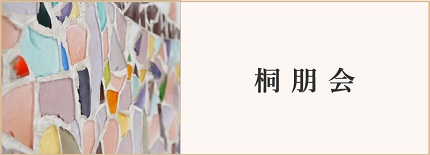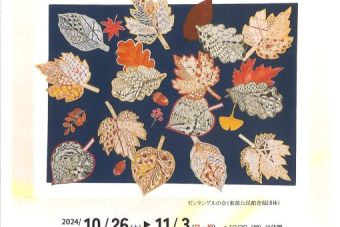桐朋女子ピックアップ一覧
中学3年(白) MF練習から観劇「ゴースト&レディ」
- 中3
ボランティアグループ「空」 『布田わくわくひろばまつり』に参加しました
- 部活動
中学1年 都内見学
- 中1
10月25日(金) 中学1年生の都内見学が実施されました。前期の武蔵野巡検に引き続き、後期の社会科見学です。
日本橋から京橋、最後は銀座の商店街を目指して歩いて都内をまわります。日本銀行本店を外から見学して新紙幣の話題が膨らんだり、銀座の商店街の実地調査をおこなったりと、あっというまの半日でした。普段見慣れない風景光景を写真におさめたり、建物の階層を観察したり、商店街ではどのような客層が利用しているのかなど、主に経済の機能について見学し、冬休み明け提出のレポート作成に取り掛かります。
平日で出勤時刻とも重なる時間帯であることもあり、三越前駅から銀座駅までのあいだに、桐朋女子の卒業生の方や保護者の方に何名かお声をかけていただきました。以前と変わらずホンモノに触れることを大切にしているのですね、と懐かしい様子でいらっしゃいました。
【中学剣道部】 令和6年度第9ブロック秋季新人剣道大会 準優勝
- 部活動
【中学陸上部】第77回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会
- 部活動
先日の土曜から日曜にかけて、中学陸上競技部の生徒が支部対抗大会に参加しました。
この大会は都内の23区、27市が支部ごとに代表選手を選抜し、各種目の得点で競うものです。当然、記録の良い選手が選抜されますし、調布市の代表として戦うので、参加するだけでも光栄なことです。
この大会に、桐朋女子からは個人種目で5人が参加しました。また、共通の4×100mリレーにもチームとして参加することができました。
当日は各選手が力を発揮しましたが、とくに3年800mに出場した選手は2分23秒13の好記録(これは自己ベストです!)を出して、見事5位に入賞することができました。
レベルの高い大会で結果を残すことは大変なことです!よく頑張りました。
このような大会でたくさんの刺激を受け、次のシーズンに向け、またしっかりと鍛錬を重ねていきます!
【中学バレーボール部都大会出場決定!】新人大会第9ブロックベスト4
- 部活動
先日行われた新人大会にて、中学バレーボール部が第9ブロック(調布市・府中市・三鷹市・武蔵野市・狛江市)ベスト4まで勝ち上がり、見事、部の目標としていた都大会出場を決めました!
都大会進出を決めたのは、数十年ぶりの歴史的快挙です!
調布市予選では2試合ともフルセット負けを喫し悔しい思いも味わいましたが、なんとか調布市3位で勝ち上がり、ブロック大会では三鷹市予選1位のチームをフルセット勝ちで破り、その勢いのまま都大会出場(都ベスト64)を達成しました!
監督も嬉し泣き。『人生で勝って泣けることなんてそうはないです。選手たちの頑張りとサポートしていただいた保護者や高校チームの熱心な指導あってこそのこの結果なので、本当に感謝です。そして都大会では、負けたチームの分までブロック代表として恥じない戦いをしたいと思います。』とおっしゃっていました。
今回の写真も、大会当日応援に来てくださった保護者の方々からいただいたものです。ありがとうございました。
都大会は11月17日より開催されます。引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします。
高校1年(青) 八ヶ岳合宿後半 3日目
- 高1
高校1年(青) 八ヶ岳合宿後半 2日目
- 高1
東部公民館の文化祭で企画や展示の発表をします。
- 全校
高校1年(青)八ヶ岳合宿前半最終日&後半一日目
- 高1