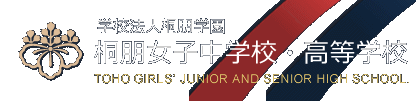桐朋女子ピックアップ一覧
中学2年 八ヶ岳合宿の報告
- 中2
中学2年生の八ヶ岳合宿が、無事終わりました。
1日目。農業体験。ジャガイモと小松菜の収穫を体験。
2日目。朝の体操。そして、何とか天気ももって、高原寮から清泉寮、美しの森へハイキング。帰寮後、家族へのハガキを書く企画もあり。
3日目。雨天のため飯盒炊爨が叶わず、寮での豚汁、採りたてレタスのサラダ作り、マシュマロ焼き、八ヶ岳委員による班対抗での企画となり。クイズあり、松ぼっくりを使っての工作あり、農業の抱える問題を考える問題解決のお題あり、という様々なジャンルの難問に、班でチャレンジ。夜はキャンプファイヤー。
4日目。帰京。あっという間の3泊4日。学年の絆も深まりました。
中学2年紫 総合の時間
- 中2
東京演劇集団「風」によるバリアフリー演劇
『ヘレン・ケラー~ひびき合うものたち』観劇
昨年度3月、学年で、東京演劇集団「風」の俳優、西垣耕造さんによる「コミュニケーション・ワークショップ~バリアフリーアクティビティ」を体験し、「行動(action)と反応(reaction)が共に共鳴し合って循環することで、面白い集団になっていく」など、これまで意識していなかった視点で生活を見つめ意識する視点をもてたところで、
本日(6月5日)はその第2弾、「風」のバリアフリー演劇『ヘレン・ケラー~ひびき合うものたち』を観劇しました。観劇終了後、学年を代表し2人の生徒から感想を伝え、バックステージツアー(舞台裏見学)や、サリバン先生役と手話通訳役者さんのお二方との座談会などの機会もいただき、充実した総合の時間を過ごすことができました。
(以下、「風」さんのパンフレットより引用)
“バリアフリー演劇とは、目が見えない人たち、耳が聞こえない人たち、目が見えて耳が聞こえる人たちが同じ空間で、演劇を一緒に楽しめるようにする新しい試みです。各分野の専門家、演出家、俳優が議論を重ね、共同制作しました。セリフの字幕表示や音声ガイドを追加し、手話通訳者も出演者の一人として演じるなど、シナリオや演出にも工夫を加えました。この試みをきっかけとして、『バリアフリー演劇』がムーブメントとなることを目指しています。”
中2紫 体育祭 解団式
- 中2
5月29日(水) 先週5月22日に実施された体育祭の表彰式をしました。
応援交歓と団体徒手については、当日の演技の動画をみんなで視聴しました。
実行委員、各種目のリーダー、そして応援企画委員から、今年の反省と来年に向けての思いが話されました。今年の振り返りを経て、来年に向けて体育祭への目標が見えてきたようです。
Aブロックミニ体育祭
- 中1
- 中2
5月15日(水) 体育祭まで1週間となりました。Aブロック中学1・2年生のみが参加するミニ体育祭では、種目のルール確認もかねて本番に近い形で競技が行われます。中学2学年での競技進行ではありましたが、各学年ともに大きな声援と熱戦で、来週の体育祭本番への気合いが感じられました。
中学1年・2年 特別時間割合同企画
- 中1
- 中2
津軽三味線&和太鼓ユニット「ごちえもん」のみなさんによる演奏会
3月13日(水) 日本の伝統楽器である「三味線」と「和太鼓」のジョイントライブ。中学1年生と2年生の2学年で、迫力のある音と懐かしい響きを堪能し、充実したひとときを過ごしました。
中2白 ビブリオバトル本選!
- 中2
2月21日(水)にビブリオバトルの本選が行われました。各々が本を紹介し、その本に対する概要と熱意を発表して競います。事前の予選で選ばれた15人は、限られた時間の中で本の面白さを伝えようと頑張っていました。審査は学年の生徒全員で行います。どの本に対しても真剣に聞き入っていました。
中学百人一首大会
- 中1
- 中2
- 中3
1月17日(水) 中学百人一首大会が開催されました。桐朋女子では、中学3年間で“百人一首の百首を全て覚えること”を目標にしています。そして毎年1月には、3学年の対抗戦で、百人一首大会が開催されます。「源平合戦」の形式で、2~3人が1チームになって、他学年と競い合います。今年も昨年に引き続き、中学3学年の全HR教室で、熱い闘いが繰り広げられました!中学1年生は初めての百人一首大会でしたが、先輩に追いつこうと頑張りました。さすが、中2、中3の先輩は強かった!
中学ミュージックフェスティバル
- 中1
- 中2
- 中3
12月19日(火) パルテノン多摩にて、ミュージックフェスティバル(MF)が開催されました。MFは中学3学年で開催される合唱コンクールです。10月ごろから各クラスで曲決めが始まり、約2か月間の練習期間を経て本番を迎えます。
どのクラスも練習の成果を存分に発揮し、演奏を届けました。また運営の中学執行部でも、早くから下見や準備を行い、昨年度を活かしたスムーズな行事運営ができました。MFという行事を通して、中学3学年ともに沢山の収穫があったことと思います。
中学2年 社会科見学
- 中2
中学2年 八ヶ岳合宿 後半
- 中2
前半のABC組に続き,後半のDE組も無事八ヶ岳合宿を終了しました。前半は曇りの日もあり,若干雨も降ったりと,屋外での活動が制限された時もありましたが,後半は天候にも恵まれ,ハイキングも全行程踏破し,2日目のレクである花火もとても楽しむことができました。