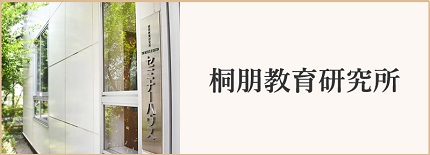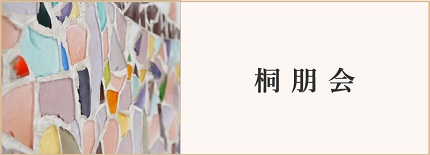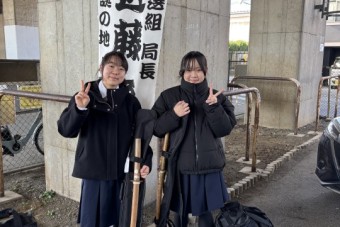桐朋女子ピックアップ一覧
卒業生による進路講演会(大学生編)
- 高2
高1白 体育の授業風景②
- 高1
剣道部 中1 一級審査
- 中1
- 部活動
中1黄色 英語スピーチ発表会
- 中1
中1黄色 初めての調理実習
- 中1
高1白 体育の授業風景
- 高1
音楽部音楽班 第三支部演奏会
- 部活動
1月25日(日) 武蔵野市民文化会館にて、第47回第三支部演奏会が行われました。
第三支部の私立学校の音楽に関する部活が参加し、年に一度開催される演奏会です。
音楽部音楽班はオーケストラで、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン作曲の「交響曲第5番ハ短調作品67」より第1楽章を演奏しました。「運命」という通称で知られている曲で、今年度は文化祭とオーケストラフェスタでも演奏しています。練習を重ねるたびに音の重厚感や迫力が増し、この日の本番では今までで一番良い演奏ができました。
また、放送部の中学3年生2名が会場アナウンスを務めました。例年高校生が担当することが多いのですが、今年は高校生が大会を控えているため、中学3年生に大役が任されました。難易度の高いアナウンスでしたが、落ち着いて役目を果たしました。
どの学校も、私学ならではの個性が表現された素晴らしい演奏会でした。
志望理由書事前指導講演会
- 高2
調布市政施行70周年記念・第70回調布市民駅伝競走大会
- 部活動
陸上競技部 調布市市民駅伝競走大会で出場全チーム入賞を果たしました
- 部活動